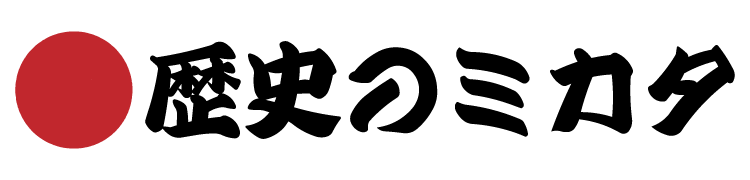清少納言は、紫式部と並んで平安を代表する女流作家として有名です。
代表作は随筆『枕草子』で、紫式部とはライバルだったと言われています。
そんな清少納言の生涯は、どのようなものだったのでしょうか?
その生涯と、どんな人だったのかを示すエピソードなどを紹介します。
清少納言の生涯
清少納言は、村上天皇の命で昭陽舎に置かれた和歌所の寄り人である梨壺の五人の1人の、著名歌人である清原元輔の娘です。
誕生年は不明で、少なくとも974年よりは前とされています。
清少納言は女房名であり、本名は不明ですが清原諾子という説があります。
清は清原に由来するものと考えられますが、近い親族に少納言職のものがいないとされているため、由来は不明です。
974年に父が周防守に赴任した際は同行し、4年を過ごしています。
この経験は、枕草子の中で生かされています。
ここで過ごす間に京への思いを募らせたことが、宮廷への憧れになったと考えられています。
981年に陸奥守の橘則光と結婚して、翌年に則長を産んだものの夫とのそりが合わなかったため、離婚してしまいます。
ただし、それ以降も交流はあったとされています。
後に摂津守の藤原棟世と再婚して、娘の小馬命婦をもうけています。
993年の冬頃からは、私的な女房として中宮定子に仕えていました。
昔からあこがれていた宮廷での生活が始まり、かなり喜んでいたようです。
女房は30人ほど教養が高い女性がいたのですが、その中でも特に博学であり気が強かったことが禎子に気に入られ、恩寵を賜っています。
当時は、漢文と言えば男性が学ぶものとされていたのですが、清少納言は幼少時から父に教え込まれていたため、和歌や漢詩の知識が豊富だったのです。
しかし、995年に道隆が逝去してから、この生活に陰りが見え始めます。
996年に、定子の兄は道長の策謀によって流刑となりました。
その際に、清少納言は道長のスパイだという流言が流れたため、家に引きこもるようになりました。
しかし、定子は自身にも母の他界や屋敷の消失などのつらい出来事があったため、清少納言を近くにおいて慰めて欲しいと思っていました。
そのため、清少納言に当時基調だった紙を20枚贈っています。
清少納言はそれを喜び、宮廷生活の様子を書き込んだ枕草子を書いていきます。
そして定子の元に戻ったのですが、1000年に定子が出産と共に亡くなってしまい、それからしばらくして宮仕えを辞めています。
その後の清少納言の生涯は不明とされているものの、断片的な資料からは一時摂津国へと下ったと思われます。
没年も不明ですが、古事談では没落した様子が記されています。
清少納言のエピソード
清少納言と言えば、平安時代を代表するキャリアウーマンの1人です。
その人柄などを表すエピソードも、いろいろと残されています。
清少納言は、どのような人物だったのでしょうか?
清少納言の父は著名な歌人だったのですが、曾祖父の清原深養父も古今和歌集に歌が収録されるほどの有名な歌人でした。
しかし、清少納言は和歌が苦手だったのです。
先祖代々和歌を得意とする家計だったのがプレッシャーとなり、歌会などは断っていました。
定子が主宰する歌会にすら、顔も出さなかったのです。
定子は、著名な歌人の娘なのになぜ今夜の歌会に加わらないのか、と疑問を呈したことがあります。
その際は、歌人の娘と言われない立場なら真っ先に読んでみせると答えていました。
枕草子のような随筆には長けていたのですが、和歌については父や曾祖父に気後れしてしまい、読もうとは思わなかったのです。
これについては、かつて周囲の人に何か言われたことがあるのかもしれません。
また、清少納言と言えば紫式部のライバルとして有名です。
仕える主も、一条天皇の皇后である定子と中宮の彰子と、ライバル関係にあります。
それぞれの部下で、作家としても有名な女性同士として、互いを意識するのは当然と言えるでしょう。
実際に、紫式部日誌には清少納言のことが書かれていて、大した学問もないのに利口なふりをしている嫌な女、と評されています。
それに先んじて、清少納言も紫式部の夫の衣装をけなした文章を書いていたとされています。
しかし、実際にはこの2人が宮廷に入っていた期間は、かぶっていなかったはずです。
紫式部が彰子の教育係となって宮廷に入った時、すでに清少納言は宮廷から去っていたのです。
そのため、直接2人が接する機会はありませんでした。
それにも関らず2人がライバル視していたのは、紫式部が清少納言の枕草子を生み出した才能に嫉妬していたことや、仕える人物がライバル関係だったことなどがあげられるでしょう。
まとめ
清少納言は、紫式部の源氏物語に先んじて枕草子を書き上げた、女流作家のはしりともいうべき人物です。
日本三大随筆の1つにも数えられる名作で、当時の宮廷の様子を知ることができる貴重な書物です。
生涯には謎が多い人物でもありますが、少なくともその中心となったのは宮廷で過ごしていた華やかな日々だったのだと思われます。